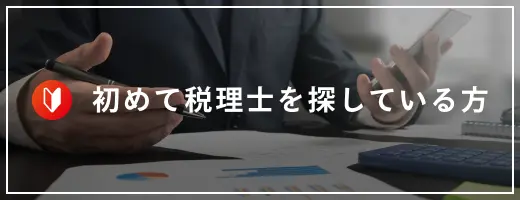BLOG
ブログ
BLOG
ブログ
 BLOG
BLOG
- 会社経営
- 税金の話
倒産防止共済の解約に注意
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)による節税手法が令和6年10月1日より一部制限されることとなりました。
倒産防止共済とは
中小企業や個人事業主が取引先の倒産などによる資金繰りの悪化を防ぐための公的な共済制度となります。
加入者は月額5,000円から20万円まで掛金を設定することができ、掛けた金額は全て損金(経費)とすることができます。
掛金は最大800万円までとなり、掛金の10倍まで無利子で借入することが可能となります。
解約時には一時金として収入となりますが、通算40ヶ月以上掛けることにより満額受け取ることができます。
倒産防止共済の節税について
決算前に利益が大きく見込まれる際に、前納をすることによって最大240万円を一気に損金として計上することが可能となります。
その後、従業員や役員の退職時、設備投資や大きな赤字決算などの際に解約することで退職金などと一時金を相殺させ、資金を補填するという形が一般的に利用されているかと思われます。
倒産防止共済の制限
従来、中小企業や個人事業主の連鎖倒産を防ぐ目的の制度ではありましたが、節税としての利用が増えてしまったため2024年の税制改正により、一部制限となりました。
制限内容は、従来解約後再加入することにより再び損金として扱うことが可能となっておりましたが、令和6年10月1日以降に解約されますと、解約後2年間は損金として認められなくなります。(掛金の積み立ては可能です)
「今期は営業成績が良くないから解約して来期は営業成績が良くなる見込みだから倒産防止共済を使って節税しよう・・・」
といった手法が使えなくなってしまいます。
令和6年10月1日から始まる制度となりますので、節税目的で利用されている事業者様は今後の解約タイミングをしっかり見極めることが必要となります。
顧問税理士と相談して今後どのようにするか検討してみてはいかがでしょうか。
- PROFILE
-

愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。
こちらの記事もおすすめ RECOMMEND

- 税金の話
令和7年度税制改正大綱から見る年収103万の壁について
年収103万円の壁:令和7年税制改正大綱から考える 令和7年税制改正大綱が発表され、「年収103万円の壁」に関する議論が再び注目を集めています。このコラムでは、年収103万円の壁が抱える問題点、今回の改正で何...

- 会社経営
電子帳簿保存法 電子保存が義務化される?
電子取引情報を電子保存することが義務化される動きが昨年ありましたが、義務化が2年間延長されるという内容が2022年の税制改正によって適用となりましたので、その内容についてご紹介します。 まず電子帳簿保...

- 会社経営
対象期間延長&助成率引上げ!! 雇用調整助成金
『雇用調整助成金(新型コロナ感染症の影響を踏まえた特例措置)とは?』 新型コロナ感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた際に従業員の雇用維持を図るために【雇用調整(休業)】を実施する事業主に対...