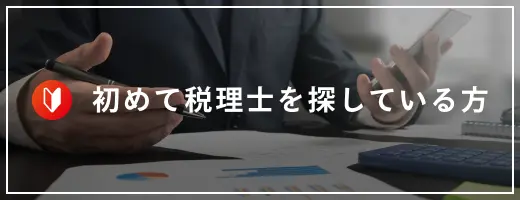BLOG
ブログ
BLOG
ブログ
 BLOG
BLOG
- 税金の話
ふるさと納税と定額減税
令和6年の税制改正によって、「定額減税」が実施することが決定されました。
この制度では、納税者とその扶養家族1人あたり、所得税が3万円、住民税が1万円減税されます。
6月から始まったこの制度について耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
今回の記事では「定額減税」が「ふるさと納税」にどのような影響を与えるかについてお話しします。
〇ふるさと納税とは
ふるさと納税は、自分の生まれ育ったふるさとや応援したい自治体に寄付をすることで、税金の控除を受けることができる制度です。
寄付をすることで、その自治体の名産品を返礼品として受け取ることができます。
控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。
しかし、給与所得者で寄付先の自治体が5団体以下などの要件を満たす場合には、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請するだけで控除を受けることができます。
〇ふるさと納税の上限額と定額減税
ふるさと納税の寄付上限額は、個人の所得や家族構成などによって決まります。
ふるさと納税のサイトで自身の所得などを入力することで、誰でも簡単におおよその上限額を確認することができます。
上限額を超えた場合、その超過分は控除の対象外となります。
冒頭でもお話しした通り、定額減税は1人あたり、所得税が3万円、住民税が1万円減税される制度です。
では、定額減税によってふるさと納税の上限額は変わるのでしょうか?
「令和6年度税制改正の大綱」に下記のような記載があります。
(6)以下の額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、特別控除の額を控除する前の所得割の額とする。
①都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
参考:令和6年度税制改正の大綱
これは、ふるさと納税の上限額が定額減税「前」の住民税の金額を基に決められることを意味します。
定額減税「後」の住民税の金額を基にした場合、すでにふるさと納税を行った人に不利益が生じる可能性があるためです。
このように、ふるさと納税をしても損をすることはなく、定額減税が上限額に影響を及ぼすことはありません。
〇最後に
今回は「定額減税」と「ふるさと納税」の関係についてお話ししました。
ふるさと納税を行う際には、シミュレーションで自分の上限額を確認し、上限額を超えないように気をつけましょう。
また「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する場合、翌年の1月10日までに申請の手続きを行ってください。
万が一忘れてしまった場合は、確定申告を行うことで控除を受けることができますので、忘れずに行いましょう。
また、総務省は2025年10月から、仲介サイトからのポイント付与を禁止すると発表しています。
今後もふるさと納税の制度の見直しが行われる可能性があるため、定期的に情報をチェックすることが大切です。
「ふるさと納税」を利用して、お得に各地の名産品を楽しんでみてはいかがでしょうか?
- PROFILE
-

愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。
こちらの記事もおすすめ RECOMMEND

- 税金の話
ふるさと納税で被災地の支援ができる!
被災地への寄付はふるさと納税でも行えます。 ふるさと納税・・・2008年に創設された「自分が応援したい自治体に寄付する」ことができる制度 各地で自然災害による多くの災害が発生し、多くの被...

- 税金の話
消費税の原則課税と簡易課税
事業を営む法人、個人は原則消費税を納付しなければなりませんが、納税の義務が免除される場合があります。 基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)による判定 基準期...

- 税金の話
償却資産税とは?
償却資産税とは? 「償却資産税」という言葉、聞き慣れない方も多いかもしれません。 これは、企業や個人事業主が事業で使用する固定資産に課される地方税の一つです。 償却資産税は、固定資産税の一部で...