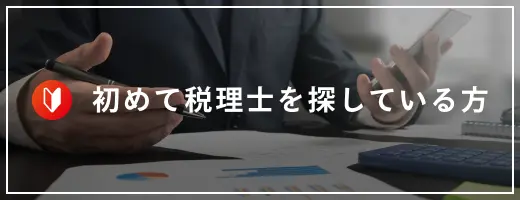BLOG
ブログ
BLOG
ブログ
 BLOG
BLOG
- 相続・贈与
- 税金の話
使えなくなる!? 110万円の非課税贈与
「110万円の贈与でも贈与税が課税されるようになる」といった話を耳にしたことはないでしょうか?
この話を聞いて、「相続税対策のために少しずつ贈与してきているのに、もうできなくなってしまうの?」と思われる方も多いかと思います。
110万円までの非課税での贈与については、以前から相続税対策として利用されてきました。
相続が発生した場合、相続人の持っている預貯金や役員借入金などの資産は相続財産として相続税の計算に含まれるため、相続が発生する前に少しずつ資産を子や孫へ移動させることで相続税の負担を抑えることができます。
一度に高額の資産を移動させると贈与税の負担がかかりますが、年間で110万円までであれば贈与税を課税されることなく贈与をすることができます。
これを利用して、毎年預貯金を贈与したり、法人役員であれば役員借入金を贈与して相続税の対策をすることができます。
しかし、この非課税での贈与ができなくなってしまうのであれば、相続税対策として贈与をしても贈与税を課税されてしまうことになってしまいます。
相続税対策として贈与したのに贈与税で税金をとられてしまうのでは、金額によってはメリットがなくなってしまいますね。
110万円以内の非課税での贈与については、いずれはできなくなってしまう可能性があります。
いつから制度が変わるのかはこの記事を作成した頃には発表されてないですが、いつの間にか非課税での贈与ができなくなっていた、思ったより相続税の負担が大きくなりそうだ、などといったことがないよう、相続税については事前に検討しておく必要があるでしょう。
- PROFILE
-

愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。
こちらの記事もおすすめ RECOMMEND

- 税金の話
仮想通貨取引の税金申告について|確定申告で押さえるべき3つのポイント
昨年から、ビットコインに代表される、仮想通貨の取引が大きく報道されてくるようになりました。 投資に関する判断は、自己責任・自己判断でお願いしますが、これに関する税金を忘れずに申告お願いします。 ...

- 会社経営
- 会社設立
- 税金の話
法人成りで節税ができる!?
確定申告が終わり、思ったより税金が高くて節税策を探している個人事業主の方は多いのではないのでしょうか。税負担の大きい個人事業主は、法人成りすることで所得税などが節税できる可能性があります。ここでは...

- 税金の話
副業の確定申告義務について
確定申告について本腰をいれていく時期になりました。今年は新型コロナウイルスの影響で本業がうまくいかず副業を始めましたという方も多いのではないでしょうか。今回は副業をされた方の確定申告についてお話し...