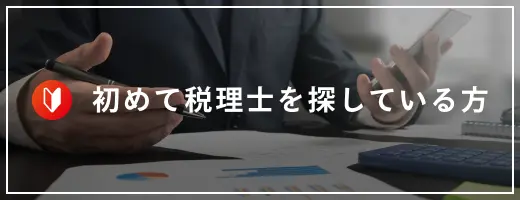BLOG
ブログ
BLOG
ブログ
 BLOG
BLOG
- 税金の話
土地の評価額(地価)は150年前に生まれたもの?
固定資産税・相続税の計算基準として、大きな比重を占めるものに、土地の評価額(地価)があります。
公示地価・基準地価など耳にしたことがあるでしょうが、そもそも地価とは、いつから存在しているのでしょうか?
今年は明治維新150年
今年は、明治維新150年です。
大政奉還に始まり、四民平等・廃藩置県・文明開化…など、歴史の時間に、四文字熟語が多く出てきたことが思い起こされます(覚えるのが面倒だったと、個人的には)。
その1つに、地租改正があります。江戸時代までの年貢徴収方法(物納)に代わり、地価の3%を税金と決めた制度です。土地の私的所有権も認められました。
このとき、初めて、日本において地価という概念が生まれています。
では、この地価金額をどのように決めたのでしょうか?
地価の決め方
地価×3%=納税額のため、手間をかけて土地評価をしたのでしょうか。実は、納税額(江戸時代の年貢相当額を金銭評価)÷3%=地価 と、税額から逆算して決めています。そのため、地租改正反対一揆が起こり、税額を2.5%に下げました、と歴史で習いました。
ここで注目してほしいのは、税率を下げただけで、地価そのものを下げていないことです。江戸時代の年貢相当額から決めた地価のため、スタート時点から土地の価格が高めになっています。
その後、明治以降に日本経済が発展したこともあり、当初から高かった地価も上がり続けたのです(ひと頃言われた、土地神話です)。
このように、歴史で習った地租改正が、現在の地価基準につながっています。日本に地価が生まれてから、まだ150年にもなりません。
ところで、なぜ、地価が下がっても固定資産税は下がらないことがあるのでしょうか? 地価と固定資産税額が、必ずしも比例していないことが原因です。その理由は…次回お伝えします。
- PROFILE
-

愛知県で30年以上、3,000を超える企業・個人様に対して税に関するサポートを実施してきた税理士法人です。資金調達や創業支援など税理士顧問として経営のサポートをすることはもちろん、クラウド会計の導入支援もできる経理代行業務、生前贈与からご相談いただける相続対策など、多岐にわたるサービスを提供しています。
こちらの記事もおすすめ RECOMMEND

- 会社経営
- 税金の話
- その他
インボイス制度の対応 ~振込手数料について~
令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりました。 今回は、ほぼ全ての事業者が対象となります「振込手数料」についてのインボイスの対応をご紹介させて頂きます。 【パターン別】インボイスの対応につい...

- 税金の話
忘れがちな不動産を売却したときの税金について
株価の上昇傾向がみられ、かつ地価も上昇…と、バブル初期と同じ経済情勢がみられつつあります(バブル前後のように、乱高下しないことを祈ります)。 今回、個人が不動産を売却した場合に、よくある忘れ物をお...

- 相続・贈与
- 税金の話
使えなくなる!? 110万円の非課税贈与
「110万円の贈与でも贈与税が課税されるようになる」といった話を耳にしたことはないでしょうか? この話を聞いて、「相続税対策のために少しずつ贈与してきているのに、もうできなくなってしまうの?」と思わ...